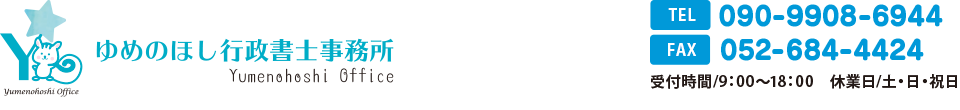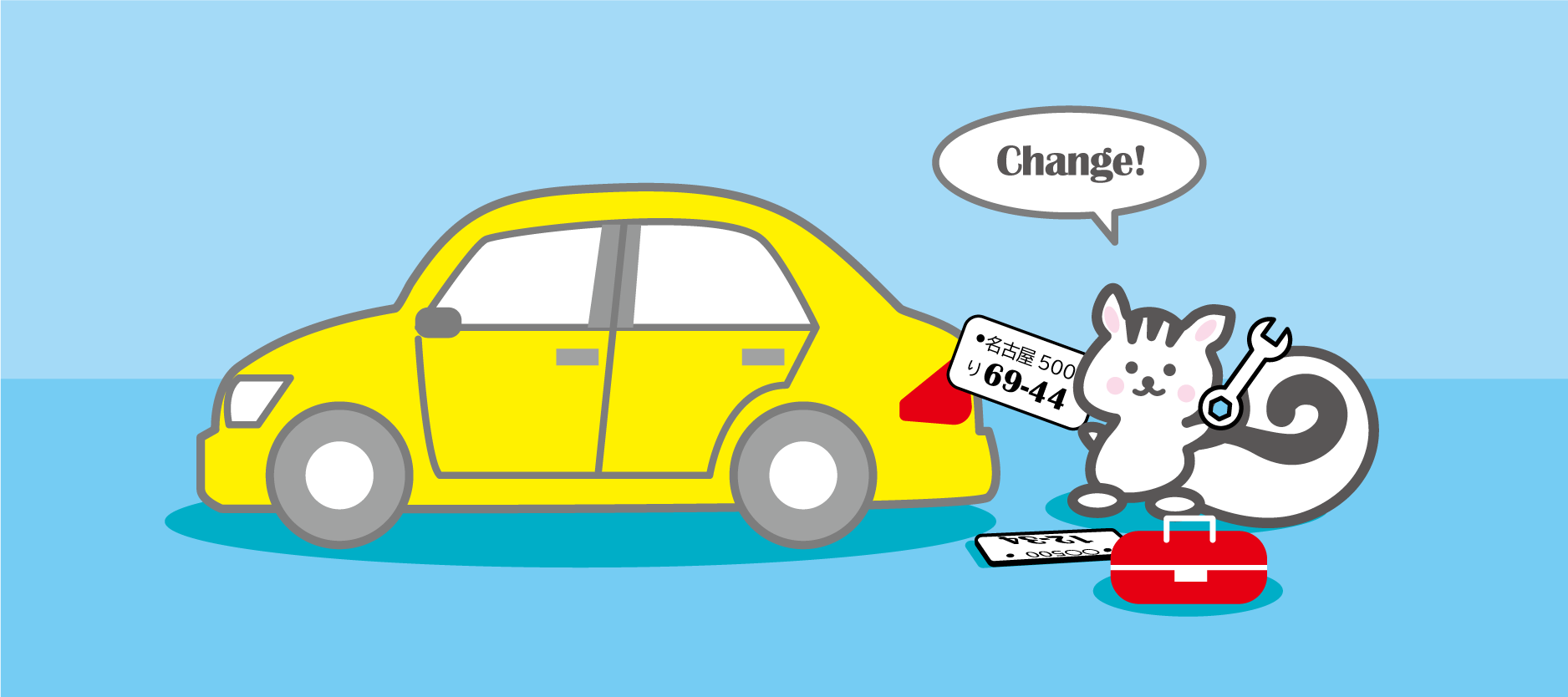相続する財産の中に軽自動車があると知ったとき、すぐに名義変更の手続きを始めて良いものなのでしょうか。
誰が自動車を相続する権利があり、どこで、どんな手続きを行わなければならないか、などよくわからないことばかりですよね。自動車にしても、そのまま使用し続けたい方もいれば処分したい方だっています。
この記事では相続する財産の中に軽自動車があるときに、最初に確認しておくポイントと手続きの流れついてお話しします。

この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。
最初に確認しておくポイント
相続する財産の中に軽自動車があると知ったとき、名義変更や処分の手続きを進める前に確認しておかなければいけないポイントがあります。
相続がはじまってすぐに軽自動車の手続きを行うと、手続きそのものが上手く進まなかったり、親族の間でトラブルになってしまうおそれもあります。
また、知らず知らずのうちに法律違反をしてしまうことだってありえます。
そうならないためにも、まずは次のことを確認しましょう。
- step1所有者を確認しましょう
はじめに、相続する軽自動車の所有者が亡くなられた方になっているかを確認しましょう。
所有者がローン会社やリース会社等になっている場合には名義を変更することができません。
所有者はどのように確認すれば良いの?
昔の車検証には所有者が記載されていました。しかし2023年1月より車検証が電子化されたため、所有者の情報はICチップへ内蔵されることになりました。
電子化された車検証に内蔵されているICチップは、車検証を専用のアプリへ読み込ませることにより所有者等の内部情報を確認することができます。
所有者がローン会社になっているときはどうすれば良いの?
自動車の所有者がローン会社になっているときには、その自動車はローン会社の持ち物ということになりので、車本体は相続財産の対象から外れますが、ローン(借金)は相続の対象となります。
このようなときには、ローン会社に契約者が亡くなったことを伝えたうえ、どういう契約内容になっているのか、自動車ローンは残っているのか、残っているとするとどれくらいなのか、それとも支払いが終わっているのか、など、今どのような状況になっているかを確認しましょう。
現状をしっかりと把握したうえで、自動車を引き続き使用したいのか、相続放棄を行うか、などの選択をします。
所有者がリース会社になっているときはどうすれば良いの?
所有者がリース会社になっているときは、その自動車はリース会社のものですので相続財産の対象から外れます。
まずはリース会社に連絡を入れ、契約者が死亡したということを伝えましょう。
契約者が死亡した場合、リース契約は強制的に解約となることが一般的ですので解約の手続きを進めましょう。
しかし、亡くなられた方が自動車を使用していたという事実やリース会社と交わしてした契約、違約金などは残ります。
契約者の死亡によりリース契約を強制的に解約すると中途解約の扱いとなり違約金が発生します。
中途解約の違約金は契約者が支払うことになっているため、その契約者の相続人が違約金の支払いを引き継ぐこととなります。
亡くなられた方のプラスの財産と違約金などのマイナスの財産を考慮して、相続をするのか、相続を放棄するのかを考えなければなりません。
- step2亡くなられた方の国籍を確認しましょう
亡くなられた方の国籍を確認しましょう。日本以外の国籍の方が亡くなった場合には、その国の法律によって相続を進めなければいけません。
- step3遺言書が残っていないかを確認しましょう
亡くなられた方の遺言書が残っていないかを確認しましょう。生前に遺言書を作成していたような言動がなかったかを思い出してみましょう。
自筆により作成された遺言書を見つけたときは注意して下さい
自筆で作成された遺言書を発見した相続人は、民法第1004条の規定により、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせることにより、その内容を明確にして偽造を防止するための手続です。
そして、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封してはいけません。
自筆で作成された遺言書を家庭裁判所へ提出することを怠ったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、または家庭裁判所外において遺言書を開封をした者は、民法第1005条の規定により5万円以下の過料に処されるおそれがあります。
- step4相続する権利のある人たちが誰なのかを把握しましょう
亡くなられた方の財産を相続する権利のある人たちが誰なのかを把握しましょう。遺言書が残されているときには遺言書の内容を優先させましょう。
相続する権利のある人たちはどうやって把握すれば良いの?
少し難しいですが、相続する権利のあるひとたちは以下の図のようになっています。

亡くなられた方の生まれてから死亡するまでを証明する書類を取得して、相続する権利のある人たちが誰なのかを把握しましょう。
これらの書類は除籍謄本や改製原戸籍という名称で市町村役場にて保管されています。また、これらの書類は軽自動車の名義変更を行うときに使用しますので、相続する権利のあるひとたちを確認した後も大切に保管しておいてください。
- step5誰が、どういう持ち分で軽自動車を相続するのかの話し合いをしましょう
相続する権利のある人たちが誰なのかを把握したあとは、誰が、どういう持ち分で軽自動車を相続するのかの話し合いをしましょう。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
軽自動車の名義変更手続きにおいて遺産分割協議書の提出は求められておりませんが、話し合いが終わりましたら、その内容を遺産分割協議書にして残しておくことで相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
もし話し合いがまとまらないときは家庭裁判所にて調停や審判を行い、誰が、どういう持ち分で軽自動車を相続するのか決定しましょう。
調停や審判とはどんなもの?
調停とは、裁判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が、当事者双方の事情や意見を聴くなどして、双方が納得して問題を解決できるよう、助言やあっせんを行い、当事者間で合意が成立するよう紛争の解決を図る手続です。
そして、調停が成立しなかった場合に裁判官が当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果や資料に基づいて決定されることを審判といいます。
遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい
遺産分割協議書の作成方法について詳しくお話している記事がありますので、よろしければそちらを参考にして下さい。
- step6相続する人たちの中に認知症や知的障害、精神障害のある方がいないかの確認をしましょう
軽自動車を相続する人たちの中に認知症や知的障害、精神障害のある方がいないかの確認をしましょう。
相続する人たちの中に認知症や知的障害、精神障害のある方がいる場合には、その人たちは相続の話し合いに参加したとしても、軽自動車を相続するのか、それとも相続しないのか、など物事の判断ができないことがあります。物事の判断ができないことをいいことに、軽自動車を相続させないように話の方向性を持って行かれたりすると、その人たちに金銭面で損害が生じてしまします。
そうならないようにするため、物事の判断ができない人たちの代わりとなってが話し合いに参加する人が必要となります。障害などにより物事の判断ができない人たちの代わりとなって手続きを進める人のことを成年後見人といいます。成年後見人がいない場合は家庭裁判所へ成年後見人の申立てを行いましょう。
判断能力のない方が遺産分割協議をしたらどうなるの?
認知症や知的障害、精神障害など、判断能力のない方がした遺産分割協議(法律行為)は民法3条の2項の規定により無効となったり、民法第120条1項の規定により取り消しの対象となります。
- step7相続する人たちの中に未成年者がいないか確認しましょう
軽自動車を相続する権利のある人たちの中に未成年者(18歳未満)がいないか確認しましょう。
未成年者(18歳未満)がいるとどうなるの?
特別代理人を選任しなければならない可能性があります。
相続する権利のあるひとたちの中に未成年者(18歳未満)とその親がいる場合には、親はその未成年者の法律行為を代わりに行う立場にいます。
未成年者にとって不利益な相続とならなければ何も問題はないのですが、親はこの立場を利用して、自分に有利なように自動車を相続することだってできてしまいます。親が有利に相続するということは、未成年者の子にとっては不利な相続になるということです。
そうならないように、相続する権利のあるひとたちの中に未成年者(18歳未満)とその親がいて、未成年者が不利益を受けるときには、未成年者を守るべき人の存在が必要です。その人たちのことを特別代理人といいます。特別代理人は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
なお、親と未成年者がそれぞれ法律で決められた割合で平等に相続するときには特別代理人を申し立てる必要はありません。そのときの自動車は共有名義となります。
- step8自動車をどうするか決めましょう
相続した自動車をどのようにするのかを決めましょう。どのようにするかは次の中から選ぶことができます。
- 引き続き使用する(名義変更)
- ひとまず使用しない(一時抹消)
- もう使用しない(永久抹消・廃車)
- step9決めた手続きを行いましょう
相続した自動車をどのようにするのかを決めましたら、それぞれに応じた手続きを行いましょう。次の項目にて、引き続き使用する(名義変更)、ひとまず使用しない(一時抹消)、もう使用しない(永久抹消・売却・廃車)、それぞれの場合についてお話しをさせていただきます。
引き続き使用する(名義変更)場合
相続した軽自動車をそのまま引き続き使用することに決めましたら、車検証や自賠責保険証などの名義変更を行いましょう。
- step1車検の有効期限を確認しましょう
軽自動車を名義変更するときには車検が有効期限内でなければなりません。もし車検の期限が経過しているときには継続検査を受けることから始めましょう。
- step2自賠責保険証を確認しましょう
軽自動車を名義変更するときには自賠責保険に加入していなければなりません。自賠責保険証を確認して保険期間が経過していないか確認を行い、もし保険期間が経過しているときには新しく自賠責保険へ加入しましょう。
- step3軽自動車を相続する書類を集めましょう
軽自動車を相続するための書類を集めましょう。相続するために必要な書類は次のものです。
- 亡くなられた方と軽自動車を相続して使用するひとの関係性を証明する書類(除籍や戸籍など)
- 新使用者の住民票または印鑑証明書
- step4車検証の名義変更をしましょう
車検証の名義変更は、新しく保有するひとの使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会にて行います。名義変更には次の書類を用意してから行きましょう。
- 亡くなられた方と軽自動車を相続して使用するひとの関係性を証明する書類(除籍や戸籍など)
- 新使用者の住民票または印鑑証明書(発行より3カ月以内のもの)
- 車検証の原本
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- step5軽自動車税種別割の納税義務者を変更しましょう
軽自動車税種別割の納税義務者の変更は、軽自動車を新しく保有するひとの使用の本拠の位置を管轄する市区町村にて行います。
車検証の名義変更を申請した軽自動車検査協会にて軽自動車税の変更届も受理されるため、車検証の名義変更書類と同時に提出しましょう。
- step6軽自動車税環境性能割を申告しましょう
軽自動車を相続すると軽自動車税環境性能割(旧:自動車取得税)の申告を行わなければなりません。軽自動車税環境性能割の申告は軽自動車税の納税義務者の変更と同時に行うことができます。なお、相続した自動車の軽自動車税環境性能割は非課税ですが申告をします。
- step7自動車保険の契約者を変更しましょう
自動車保険には強制保険である自賠責保険と任意保険の2種類があります。軽自動車を相続しましたら自動車保険の契約者を変更しましょう。自動車保険の変更は、加入している保険会社にて行います。
- step8保管場所の届出を行いましょう
軽自動車を相続したことにより、住所や駐車場が変わるときは管轄の警察署にて保管場所の届出を行いましょう。
- step9相続税の申告をしましょう
相続する財産が一定金額を超えるときには、亡くなられた方の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告をしましょう。
ひとまず使用しない(一時抹消)場合
相続した軽自動車をひとまず使用しないことに決めましたら、車検証等を返納したり軽自動車税を停止する手続きを行いましょう(一時抹消)。
一時抹消を行うことで軽自動車税の納税を停めることができます。
- step1軽自動車を相続する書類を集めましょう
軽自動車を相続するための書類を集めましょう。相続するために必要な書類は次のものです。
- 亡くなられた方と軽自動車を相続して使用するひとの関係性を証明する書類(除籍や戸籍など)
- 新使用者の住民票または印鑑証明書
- step2車検証やナンバープレートを返納をしましょう
車検証やナンバープレートの返納は、新しく保有するひとの使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会にて行います。
車検証等の返納には次の書類を用意してから行きましょう。
- 亡くなられた方と軽自動車を相続して使用するひとの関係性を証明する書類(除籍や戸籍など)
- 新使用者の住民票または印鑑証明書(発行より3カ月以内のもの)
- 車検証の原本
- ナンバープレート
- step3軽自動車税環境性能割を申告しましょう
軽自動車を相続すると軽自動車税環境性能割(旧:自動車取得税)の申告を行わなければなりません。
軽自動車税環境性能割の申告は、軽自動車を相続するひとの使用の本拠の位置を管轄する市区町村にて行います。
車検証やナンバープレートを返納する軽自動車検査協会にて軽自動車税環境性能割の申告も受理されるため、車検証やナンバープレートの返納と同時に申告をしましょう。
- step4軽自動車税種別割の納税義務者を変更等をしましょう
軽自動車税種別割の納税義務者の変更及び納税を停止する手続きを行いましょう。これらの手続きは軽自動車税環境性能割の申告と同時に行うことができます。
- step5自動車保険を解約しましょう
自動車保険には強制保険である自賠責保険と任意保険の2種類があります。軽自動車を相続し、ひとまず使用しないことに決めまたときは自動車保険を解釈しておきましょう。自動車保険の解約は加入している保険会社にて行います。
- step6相続税の申告をしましょう
相続する財産が一定金額を超えるときには、亡くなられた方の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告をしましょう。
もう使用しない(永久抹消・廃車)場合
相続した軽自動車をもう使用しないことに決めましたら、車検証等を返納したり自動車を解体する手続きを行いましょう(永久抹消・廃車)。
- step1軽自動車を相続する書類を集めましょう
軽自動車を相続するための書類を集めましょう。相続するために必要な書類は次のものです。
- 亡くなられた方と軽自動車を相続して使用するひとの関係性を証明する書類(除籍や戸籍など)
- 新使用者の住民票または印鑑証明書
- step2自動車の解体を行いましょう
もう使用しない軽自動車を引取業者へ渡して解体を行ってもらいましょう。
- step3車検証やナンバープレートを返納をしましょう
自動車の解体報告の連絡がなされた後、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会にて車検証やナンバープレートを返納をしましょう。
- step4軽自動車税環境性能割を申告しましょう
軽自動車を相続すると軽自動車税環境性能割(旧:自動車取得税)の申告を行わなければなりません。
軽自動車税環境性能割の申告は、軽自動車を相続するひとの使用の本拠の位置を管轄する市区町村にて行います。
車検証やナンバープレートを返納する軽自動車検査協会にて軽自動車税環境性能割の申告も受理されるため、車検証やナンバープレートの返納と同時に申告をしましょう。
- step5軽自動車税種別割の課税を停止しましょう
軽自動車税種別割の課税を停止する手続きを行いましょう。これらの手続きは軽自動車税環境性能割の申告と同時に行うことができます。
- step6重量税の還付を受けましょう
自動車を永久抹消すると、車検のときに支払った重量税が月割りで還付されます。この手続きも、車検証やナンバープレートの返納等と同時に申告をしましょう。
- step7自動車保険を解約しましょう
自動車保険には強制保険である自賠責保険と任意保険の2種類があります。軽自動車を相続し、もう使用しないことに決めまたときは自動車保険を解釈しましょう。自動車保険の解約は加入している保険会社にて行います。
- step8相続税の申告をしましょう
相続する財産が一定金額を超えるときには、亡くなられた方の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告をしましょう。
軽自動車の相続でお困りのときは
最後までお読みいただきましてありがとうございました。今回は軽自動車の相続における、最初に確認しておくポイントと手続きの流れについてお話をさせていただきました。
弊所は名古屋市在住の方を対象に自動車の相続手続きを行っている行政書士事務所です。お困りの際にはご相談下さい。